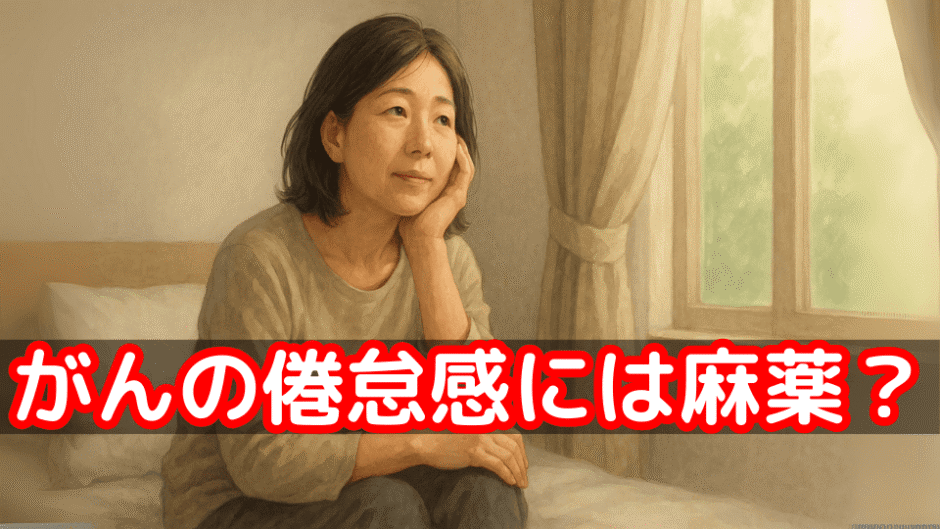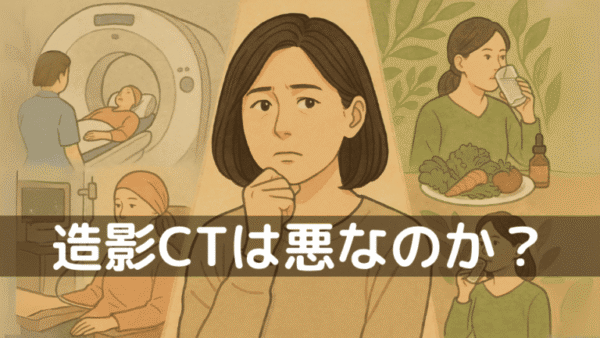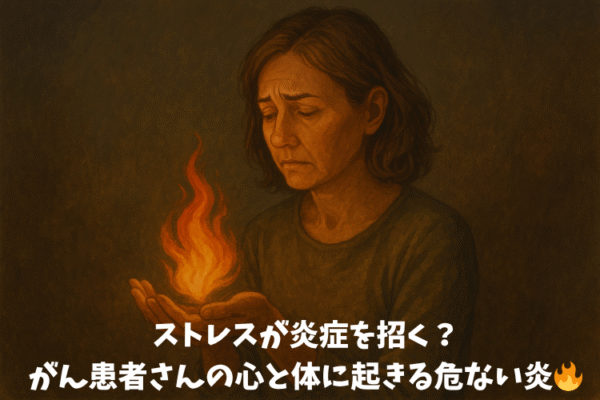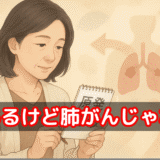患者さんの声から始まった気づき
「体が鉛のように重くて、歩くのも億劫なんです」
「寝ても寝ても疲れが取れなくて…」
抗がん剤治療を受けていたある患者さんが、そう訴えられました。
血液検査では炎症反応が高く、微熱も続いている状態。もちろん入浴すらできず、入院生活が大きく制限されていました。
そんな中でその方が一番楽しみにしてくださったのが、ベッド上での足浴と洗髪です。
「一週間に2回のその時間を、ずっと待ち遠しく思っていました」
「髪を洗ってもらった後は、体の重さを忘れて気分がスッと晴れるんです」
その笑顔を見て、私ははっとしました。
倦怠感はただの「疲れ」ではなく、人から生活の楽しみや喜びを奪ってしまう症状。
けれども、ほんの小さなケアが確かに「心と体を軽くする瞬間」を生み出せるのだと気づかされたのです。

がん患者さんの倦怠感とは? 正体を知ることが第一歩
「疲れ」と「倦怠感」は違う
通常の疲労は、睡眠や休養である程度回復します。
しかし、がん関連倦怠感(Cancer-Related Fatigue: CRF)は違います。
- 休んでも取れない
- 朝起きた瞬間からだるい
- 頭が霞んで集中できない
患者さんからはよく「鉛のように重い」「全身がもやに包まれたよう」といった表現が聞かれます。

倦怠感は“見えない症状”
倦怠感は外見から分かりにくく、職場や家庭で誤解されやすい症状です。
「仕事に復帰しても、怠けているように見られるのが一番つらい」
SNSにはこうした患者さんの声が多数投稿されています。
本人にしか分からない苦しみだからこそ、正体を理解することが対策の第一歩になります。
倦怠感の原因はひとつじゃない
倦怠感の背景には、いくつもの要因が重なっています。
- がんそのものによるエネルギー消耗
- 抗がん剤や放射線治療などの副作用
- 炎症性サイトカインの増加
- ホルモンや代謝の異常(副腎・甲状腺機能など)
- 不安や抑うつなど心理的要因
つまり、倦怠感は「気合い」や「根性」では解決できない、医学的にも認められた症状なのです。
がん患者さんの倦怠感に対するセルフケア・看護介入【ベスト3】
倦怠感は完全に取り除くのが難しい症状ですが、セルフケアや看護の関わりで少しでも軽減できます。
① エネルギーを賢く使う(省エネ)
- 家事や買い物はまとめて行う
- 必要ない移動を減らすように道具を近くに置く
- 「今日はここまでできれば十分」と優先順位をつける
👉 「やらない勇気」も大切です。
② 軽い運動を取り入れる
「疲れているのに運動?」と思うかもしれません。
しかし、研究ではウォーキングやヨガなどの軽い運動が倦怠感の改善につながることが報告されています。
- 1日10分の散歩
- ストレッチやヨガ
- 呼吸に合わせたゆっくりした動き
👉 「少し動くことで逆に体が軽くなる」ことを実感する患者さんも少なくありません。

③ 睡眠リズムを整える
倦怠感に悩む患者さんの多くが「眠っても眠った気がしない」と訴えます。
睡眠リズムを整えるだけで翌日のだるさが変わることもあります。
- 昼寝は30分以内
- 寝る前はスマホやPCを避ける
- 寝室の照明や温度を調整
👉 「眠れない夜があることも自然なこと」と伝えるだけでも安心感につながります。
それでもつらいときに——薬という選択肢もある
倦怠感は「仕方ないもの」と思われがちですが、実際には薬で和らげる方法もあります。
ここでは、がん関連倦怠感の治療に関わる薬について、代表的なものを解説します。
ステロイド薬
- 効果:短期間の倦怠感の軽減に有効とされ、食欲・気分の改善も期待できます。
- 使われる場面:強い倦怠感で日常生活が困難なとき、終末期ケアのQOL向上など。
- 注意点:長期使用は感染リスク、骨粗鬆症、筋力低下、高血糖などの副作用があるため、短期間・少量で使われることが多いです。
- 患者さんの声:「朝に少量飲んだら、午後に少し散歩できた」
医療用麻薬
- 本来の目的:がん性疼痛のコントロール。
- 倦怠感への効果:痛みが和らぐことで体を動かしやすくなり、結果的に倦怠感の軽減につながる場合があります。
- 副作用:便秘、吐き気、眠気など。適切な量の調整と支持療法(下剤など)の併用が重要です。
- 患者さんの声:「痛みが減って、家の中を歩けるようになった」
抗うつ薬・抗不安薬・睡眠薬
- 背景:不眠や抑うつ、不安は倦怠感を悪化させる大きな要因。
- 倦怠感への効果:抗うつ薬(SSRIやSNRI)が気分を安定させる。睡眠薬で夜眠れるようになり、翌日のだるさが改善することも。
- 注意点:効果が出るまで数週間かかる場合があるため、主治医との継続的な調整が必要。
貧血改善の治療(輸血・造血ホルモン製剤)
- 原因へのアプローチ:抗がん剤やがんそのものによって貧血が起こると、酸素が全身に行き渡らず強い倦怠感を生じます。
- 治療方法:赤血球輸血やエリスロポエチン製剤で改善を図る場合があります。
- 患者さんの声:「輸血後、体の重さが少し和らいだ」
薬の選択肢を知ることが、相談のきっかけになる
大切なのは、「薬がある」という事実を知っているかどうかです。
知らなければ、「仕方ない」とあきらめてしまいます。
知っていれば、診察室でこう尋ねることができます。
👉「先生、倦怠感に効く薬はありますか?」
この一言が、生活の質を変える大きなきっかけになるのです。

まとめ:倦怠感は“あきらめる症状”ではない
倦怠感は「怠け」でも「気合不足」でもなく、がん患者さんの多くが経験する医学的に認められた症状です。
- セルフケアで少しでも体を楽にする工夫がある
- それでもつらいときには薬という選択肢もある
この二つを知っているだけで、診察室で声を上げる勇気につながります。
「もう仕方ない」と思っていた倦怠感に、“和らげる方法がある” ことを知るだけでも、心が少し軽くなるはずです。
🍀関連記事のおすすめブログです。
🍀普段から体の調子を気づくための7つのポイントを紹介
🍀造影CTは被ばく量が多いって本当、余計に悪なの?
🍀ストレスは炎症反応とどう関係あるの?ストレスフリーになるためには?
 看護師の私とがん闘病の物語
看護師の私とがん闘病の物語