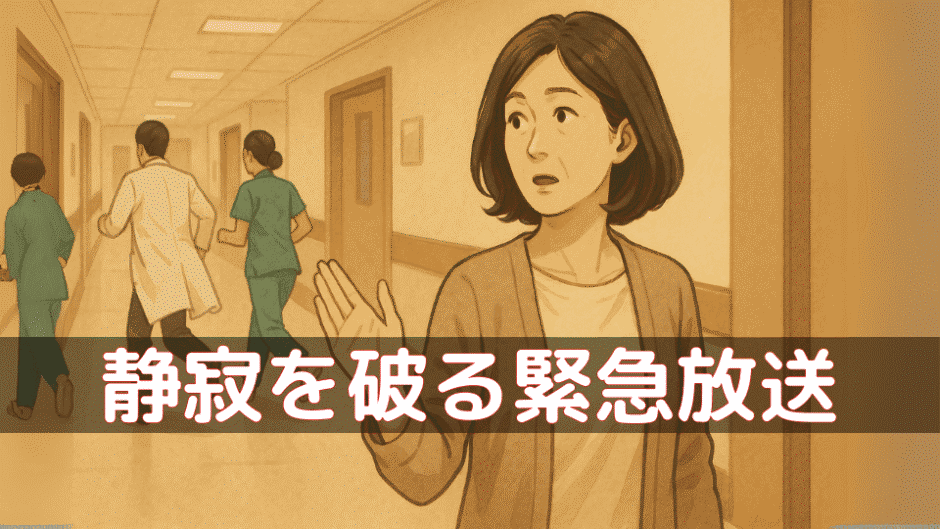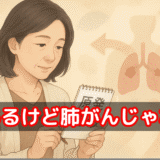はじめに
ドラマで有名になった「コードブルー」。救命救急の現場を舞台にした作品を見て、「病院では実際にこんな放送があるの?」と気になった方も多いと思います。
実は、私は高度救命救急センターで働いていた経験があり、何度も実際に「コードブルー」の放送を耳にし、その現場に走ったことがあります。
この記事では、私の実体験を交えながら、病院で使われる「コードブルー」「コードレッド」「コードグリーン」などの合図の意味や裏側についてお伝えしていきます。

コードブルーとは?現場で走り続けた救命看護師の体験
コードブルーの現場——放送が流れた瞬間の緊張感
コードブルーは、院内で急変が起きたときに医療スタッフを招集するための放送です。心停止や呼吸停止といった命に直結する場面で鳴り響きます。
私が勤務していた病院でも、何度も聞くことがありました。放送が流れると同時に、心臓が高鳴り、体が一気に緊張状態に切り替わります。
緊急バッグと共に走る瞬間
救命センターでは、常に緊急対応用のバッグを用意しています。放送が入った瞬間、そのバッグをつかんで廊下を一目散に走る。周りのスタッフも同じ方向に向かい、足音が響き渡ります。その光景は、命を救うための熱気と躍動感に満ちていました。
正直に言えば、「俺ってかっこいい」と思った瞬間もあります。それほどまでに、あの現場には使命感とアドレナリンがあふれていたのです。

カオスな現場もあった
ただし、現実はドラマのようにスマートではありません。ある病院では「手が空いているスタッフは全員集合」というルールがあり、現場は人で溢れてカオス状態。誰が指揮を執るのか曖昧になり、かえって動きにくいこともありました。この経験から、命を救うためには「仕組みと役割分担」がいかに大切かを学びました。
コードレッド:火災を知らせる合図
火災訓練でしか聞かなかった放送
コードレッドは「火災」を意味します。赤は火の色、直感的に危険を想起させるため、この色が使われています。
私自身、実際の火災でコードレッドを聞いたことはありません。聞いたのは避難訓練のときだけでしたが、それでも放送が流れると独特の緊張感が漂い、普段とは違う病院の空気を感じたのを覚えています。
コードグリーン:避難や不審者対応のサイン
訓練で経験した「サスマタ対応」
コードグリーンは、避難や不審者対応を意味することが多いです。火災や爆発の恐れ、不審者の侵入など、病院内の安全確保が必要なときに使われます。
私が勤めていた病院では、不審者侵入を想定した訓練がありました.
その際には各部署にあるサスマタを持参し、放送のあった部署に参集。複数人で取り押さえるというシミュレーションを行いました。実際の現場に遭遇したことはありませんが、患者さんやスタッフの安全を守るための備えがあると実感できる経験でした。

精神科でのコード体験
また、精神科に勤めていたときには「コードブラック」や「コードレッド」が暴力行為を知らせる合図として使われていたこともありました。精神科では、一人で対応するのは危険。必ず複数人で連携して制圧するという文化がありました。救命現場の「命をつなぐ緊張感」とはまた違う、独特の重さがありました。
自分が放送する側になったとき
造影CT室での出来事
実は私自身、一度だけ「コードブルー」を全館放送したことがあります。造影CT検査で、造影剤を投与した患者さんが急激に全身の赤みを帯び、呼吸困難に陥ったのです。血圧も一時的に測れなくなり、私一人では対応できませんでした。
そこでPHSを手に取り、震える声で放送しました。
「コードブルー、コードブルー。至急、関係者は造影CT室にお集まりください。」
「コードブルー、コードブルー。至急、関係者は造影CT室にお集まりください。」と二回繰り返すのです。
この瞬間ほど、仲間の力が必要だと痛感したことはありません。

入院患者さんやご家族にお願いしたいこと
がん患者さんを含め、多くの方が検査や治療、手術のために長い時間を病院で過ごします。その中で「コードブルー」の放送を耳にすることもあるかもしれません。
もし院内で、小走りに真剣な表情をした医療スタッフを見かけたら、ほんの少しでいいので道を譲っていただけると助かります。その先には命に関わる緊急事態があるかもしれないからです。
まとめ:色で守る命のサイン
病院で使われるコード〇〇は、決して特別な暗号ではありません。
コードブルー(急変)、コードレッド(火災)、コードグリーン(避難や不審者対応)など、色の合図はすべて「命を守るための行動指令」です。
医療者にとっては迷いなく動くためのサインであり、患者さんやご家族にとっても「対応がすでに始まっている」という安心につながります。
みなさんはもし入院中に「コードブルー」の放送を聞いたら、どんな気持ちになるでしょうか?
不安もあるかもしれませんが、その裏では命を救うために必死に走る人たちがいる——。そのことを少しでも心に留めていただければと思います。

 看護師の私とがん闘病の物語
看護師の私とがん闘病の物語