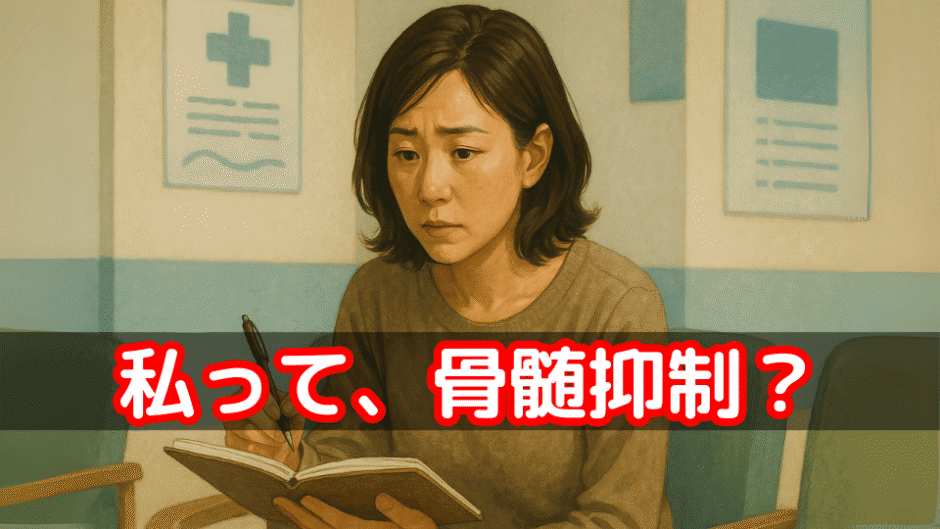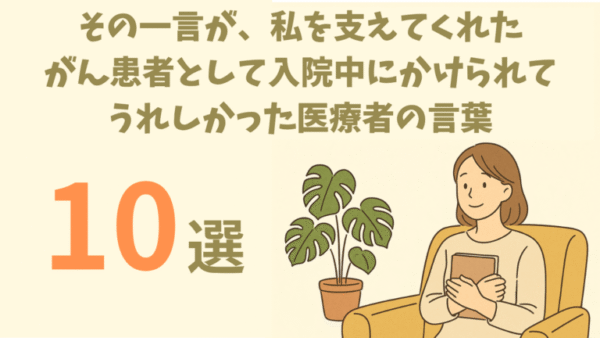「先生が使っている言葉、正直よくわからない…」
がんの治療や検査を受けると、医療者が当たり前のように口にする専門用語に出会います。聞いたことはあるけれど、意味をちゃんと説明できない――そんな経験はありませんか?
私自身、看護師として病院で働きながら、がん患者として治療を受けてきました。だからこそ「患者としては不安なのに、説明が難しい言葉が多い」というギャップを痛感しています。
このシリーズでは、病院でよく耳にするけれど意外と理解されていない医療用語をわかりやすく解説していきます。今回はその パート2。
「骨髄抑制」「ナディア」「浮腫」など、がん治療と切っても切り離せない10の用語を、私の体験や看護師としての現場エピソードを交えて紹介します。
「言葉の意味がわかる」ことは、治療を理解し、心の不安を和らげる大切な第一歩。ぜひ最後まで読んで、あなた自身や大切な人のサポートに役立ててください。
11.骨髄抑制(こつずいよくせい)
抗がん剤治療でよく耳にする「骨髄抑制」。これは骨髄でつくられる血液の成分――白血球・赤血球・血小板が減少してしまう状態を指します。
看護師として働いていた頃、私は患者さんに「感染予防と出血に気をつけてください」と繰り返し伝えていました。なぜなら骨髄抑制には、主に3つの症状があるからです。
まず 白血球減少。白血球は細菌やウイルスと戦う“免疫の兵隊”です。それが減ってしまうと感染症に弱くなります。だからこそ「手洗い・うがい・マスクの徹底」を患者さんにお願いしていました。
次に 赤血球減少。赤血球は体全体に酸素を届ける役割があります。それが不足すると体は酸欠状態になり、強い疲労感や息切れ、集中力の低下が出てきます。私は患者さんに「いつもと同じ動作で息苦しくなったら、それは赤血球減少のサイン。すぐ病院を受診してください」と伝えていました。
そして 血小板減少。普段なら小さな傷は血小板が“ばんそうこう”のようにふたをして止血してくれます。しかし、血小板が少ないと出血が止まりにくくなります。実際に「歯を磨くだけで出血が続く」「軽くぶつけただけで大きなアザになる」ということもあり、患者さんには注意してもらうようにしていました。
がんサバイバーである妹や母親は、治療中に血液検査で数値が下がり「今日は治療を延期しましょう」と言われた経験があります。今振り返ると、「これが骨髄抑制か…」と身をもって実感しました。

12.ナディア(Nadir:ナディア期)
抗がん剤治療を始めると、多くの人が直面するのが「ナディア」と呼ばれる時期です。これは投与から7〜14日後にあたり、白血球・赤血球・血小板といった血液の数値が最も低くなる時期のことを指します。
一見すると「ナディア」という言葉はおしゃれにも聞こえますが、実際にはとてもクリティカル(危機的)なタイミング。患者さんにとって一番注意が必要な時期なのです。
私が看護師として患者さんに伝えていたのは、「この時期は決して無理をせず、感染予防を徹底してください」ということ。なぜなら、ナディアが起きるのは多くの場合、自宅で療養しているときだからです。
外出や人混みを避ける、手洗い・うがい・マスクを欠かさない、体調に少しでも変化があれば早めに受診する。この行動が命を守ることにつながります。
いつもと違う、何か調子が悪いと思った時にはナディア期の可能性も高く、ご自身の体調に注意しメモしておくことが良いでしょう。そして受診時に必ず主治医・看護師にご相談ください。
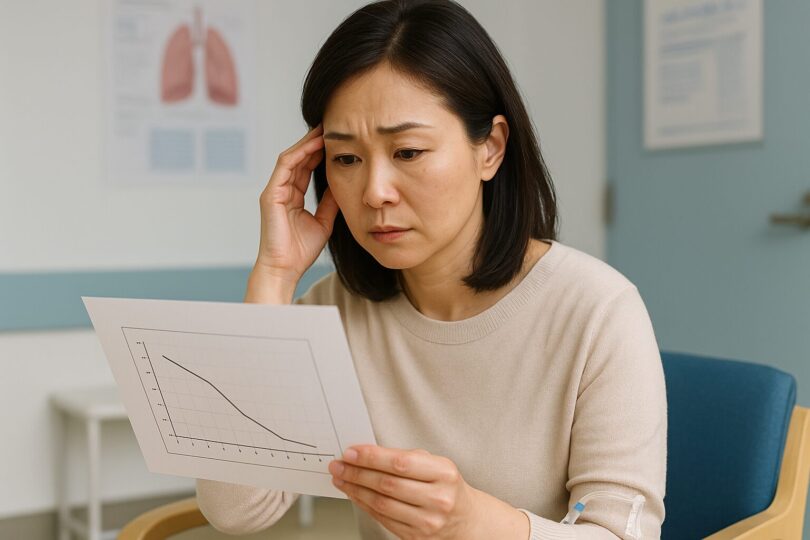
13.浮腫(ふしゅ・むくみ)
浮腫みは、目に見える健康のバロメーターだと私は感じています。普段元気に働いているときにはほとんど意識することはなくても、長時間立ちっぱなしの仕事をした日の夜に「足がちょっと重いな」と思う程度ではないでしょうか。
しかし、医療の現場では浮腫は「体のどこかが不調を訴えているサイン」としてとても重要です。私は訪問看護の仕事で利用者さんのところへ伺うとき、必ず浮腫をチェックしていました。心臓・腎臓・肝臓の機能が落ちていると、体に水分がたまりやすくなり、足や手がむくんでくるからです。
そして、がん患者さんにとって特に問題となるのが 乳がん術後のリンパ郭清による浮腫(リンパ浮腫) です。リンパ液が滞ることで腕が腫れ、皮膚が硬くなり、痛みやだるさが長く続くことがあります。このため、看護師は「手術した側の腕では血圧を測らない」というのが鉄則です。
浮腫は「ただのむくみ」と軽視されがちですが、体からの大事なSOS。私も患者さんに「昨日と比べて足の太さが違う」「靴下の跡がなかなか消えない」といった小さな変化に気づくようにお伝えしています。

14.ケモブレイン(化学療法関連認知機能障害)
「集中力が続かない」「人の名前がすぐに出てこない」「買い物や予定を忘れてしまう」――。こうした症状をがん患者さんが訴えるとき、それは ケモブレイン と呼ばれる現象かもしれません。
私は病棟で化学療法を担当していた頃、急性期の副作用を中心に観察していたため、ケモブレインのような慢性的な変化に直接立ち会うことはあまりありませんでした。ところが、X(旧Twitter)で患者さんたちの声を目にすると、「言葉が出てこない」「仕事でミスが増えた」と悩む投稿が数多くあり、現実に多くの方が苦しんでいるのだと知りました。
ケモブレインの原因は、抗がん剤による神経伝達物質への影響や、記憶をつかさどる海馬の機能障害などと考えられています。多くは一過性で、治療が終わり時間の経過とともに改善するケースが多いといわれます。
ただし、高齢の患者さんの場合は「認知症」や「うつ病」との区別も必要です。だからこそ、症状を一人で抱え込まず、医師や看護師に相談してほしいと感じています。

15.末梢神経障害(まっしょうしんけいしょうがい)
抗がん剤の副作用の中でも、日常生活に直結して困るのが 末梢神経障害 です。主にシスプラチンやオキサリプラチンといった白金製剤が原因となり、手足の神経にダメージを与えます。
症状としては、指先や足先がジンジン・チクチクとしびれるような痛み、不快感。物に触れたときの感触が鈍くなったり、逆に過敏になってしまうこともあります。
以前のブログでも触れましたが、知人の医師は膵がんの治療中に抗がん剤を受けたあと、「指先の感覚がまるでゴム手袋をしているみたいだ」と話していました。さらに、私の母も治療中に手足の動きが悪くなり、物がつかみにくくなってしまったことがあります。特に、ペットボトルのキャップを開けられず困っていた姿が忘れられません。
残念ながら、この知覚障害は治療後も後遺症として残るケースが少なくありません。時間とともに軽快する人もいますが、「完全に元に戻るのは難しい」と説明されることも多いのです。だからこそ、日常生活の工夫やリハビリ、そして「無理に頑張らないこと」が大切だと感じています。
・末しょう神経障害の代表格”しびれ” その辛さは大変なものです。それって続くの?
16.倦怠感(がん関連疲労)
がんやその治療(化学療法・放射線療法・免疫療法・骨髄移植など)に伴って、多くの患者さんが経験するのが がん関連疲労 です。
これは「ちょっと疲れたから休めば回復する」という普通の疲れとはまったく違います。強いだるさや体の重さが続き、休んでも眠っても軽減しにくいのが特徴です。活動時だけでなく、安静時にも疲労感が消えない――そんな「やばい疲れ」です。
症状は全身のだるさや強い疲れに加え、注意力や集中力の低下もみられます。原因としては、がん細胞が大量のエネルギーを消費したり、体の炎症反応を引き起こすこと。さらに、治療に伴う吐き気・貧血・栄養不良・脱水・不眠といった副作用も重なり、複合的に疲労が強まります。
看護の現場で私が意識していたのは、 運動と休息のバランス。適度な運動療法を勧めつつ、栄養や水分の摂取をサポートし、熟眠できる環境を整えることを大切にしていました。ときには昼寝を取り入れることで、体と心の回復を助けることもあります。
がん関連疲労は単純に「これをすれば治る」というものではありません。複数の原因が絡み合うため、多面的なケアが必要です。だからこそ、「疲れて当たり前」と我慢せず、ぜひ医師や看護師に相談してほしいと思います。

17.味覚障害
がん治療の副作用のひとつに 味覚障害 があります。味を感じにくくなったり、実際の味とは違う味(金属のような味や苦み)を感じるのが特徴です。原因は抗がん剤や放射線治療によって味を感じる細胞が傷つくこと、また唾液の分泌が減ることでも起こります。
味覚障害は食欲低下につながり、栄養不足を招いてしまうため、がん治療を続けるうえで大きな問題になります。実際、患者さんから「大好きだったコーヒーが苦くて飲めない」「味が全部同じに感じる」といった声をよく聞きました。食べる楽しみが失われるのは、とてもつらいことですよね。
私が現場でよくアドバイスしていた工夫を紹介します👇
- 酸味を活用:レモンや酢の物などで味覚を刺激して食欲を高める。
- 旨味を活かす:昆布だし、かつお節、味噌、醤油などを使うと苦味を感じにくくなる場合がある。
- 亜鉛を摂取:牡蠣、レバー、魚介、ナッツ、豆類などは味覚細胞の回復に役立つ。
- 食感と香りを工夫:ナッツやクルトンで歯ごたえをプラスしたり、香味野菜(ねぎ、しそ、三つ葉など)で風味を豊かにする。
- 温度調整:熱すぎると刺激が強く不快に感じることがあるので、人肌程度に冷まして食べる。
- 水分補給:こまめな水分摂取や人工唾液で口の乾燥を防ぐ。
こうした工夫で「食べられるものが少しずつ見つかった」と話してくれる患者さんも多くいました。味覚障害は一過性のことが多いですが、治療中はとてもストレスになります。だからこそ「味わう工夫」で少しでも食事を楽しめるようにサポートすることが大切だと感じています。

18.感染予防
がん患者さんにとって、感染予防は命を守る基礎です。がんそのものや抗がん剤・放射線・免疫療法などの治療によって免疫力が低下しているため、普段なら軽く済む感染症でも重症化しやすくなります。場合によっては命に関わることもあるのです。
感染症にかかると、治療の中断や延期、入院期間の延長につながり、体力だけでなく精神的な負担も大きくなります。だからこそ、私は病院で化学療法を受けて退院される患者さんに、まず一番に「感染予防を徹底してください」と伝えていました。
特に注意が必要なのは、白血球が一番下がるナディア期。免疫力が落ちているこの時期は「無理をしない」「感染しやすい環境を避ける」ことがとても大切です。
具体的な感染予防のポイント
- 手洗い・アルコール消毒:外出後・食事前・トイレ後には丁寧に。
- マスク着用と咳エチケット:人混みや密閉空間では必須。
- 接触回避:体調不良の人との接触を避け、家族も同じ対策を。
- 口腔ケア・皮膚の清潔:小さな傷や口内炎も感染の入り口になります。
- ワクチン接種:インフルエンザや肺炎球菌ワクチンは有効な予防策です。
感染予防は患者さん本人だけの努力ではなく、医療者や家族も一緒に取り組むチーム戦です。私は看護師として、患者さんが安心して治療を続けられるように「予防こそ最大の防御」と伝えてきました。

19.腫瘍マーカー
「腫瘍マーカー」とは、がん細胞がつくり出す物質や、がんの存在に反応して体内の正常細胞が作る物質のこと。血液や尿から検出できるため、がんの有無や種類、進行の目安として使われます。
有名なものでは CEA、CA19-9、PSA などがあります。これらはがんの早期発見の補助、治療効果の判定、再発や転移の早期発見につながる重要な指標です。
私の場合は遺伝性のリンチ症候群があるため、大腸がんを疑って CA19-9 を毎回の検査で追っています。また、前回の造影CTで前立腺の肥大を指摘されたことから PSA も検査するようになりました。数値が上がったり下がったりするたびに一喜一憂し、「今回は大丈夫かな…」と結果が出るまで不安で仕方がありません。
がんサバイバーにとって、腫瘍マーカーは知らないうちに“身近な存在”になります。血液検査のたびに「今日はどうだろう」と胸がざわつくのです。
ただし注意が必要なのは、腫瘍マーカーは万能ではないということ。たとえば私の罹患した尿管がんには、決定的な腫瘍マーカーは存在しません。だからこそ、腫瘍マーカーの数値だけで判断せず、CTや内視鏡などの複合的な検査を組み合わせることがとても大切なのです。

20.PET-CT
がんの検査の中でも「精密検査」として名前を聞いたことがある方が多いのが PET-CT です。これは PET検査 と CT検査 を組み合わせた画像診断法で、がんの早期発見や進行度の評価、転移の有無を高い精度で調べることができます。
PET検査の仕組み
PETでは、ブドウ糖に放射性同位元素を結合させた薬剤(FDG)を静脈注射します。がん細胞は正常な細胞よりもたくさんのブドウ糖を消費するため、FDGががんの部分に多く集まり、その放射線をPETカメラで検出して画像化します。これによって体内の細胞の代謝活動を可視化し、がんの存在する場所を特定できるのです。
PET-CTのメリット
- PETとCTの画像を融合させることで、がんの位置や大きさ、広がりをより正確に診断できる。
- 一度の検査で全身を調べることができ、転移の有無を効率的に確認できる。
- 従来の検査では見つかりにくい小さながんや、原発不明がんの診断にも役立つ。
私の体験
私は30代のときに一度PET-CTを受けたことがあります。検査前に6時間ほど絶食し、検査当日はブドウ糖に似た点滴(FDG)を受けました。トータルの検査時間はおよそ2時間半。医療保険の3割負担でも 3万5千円ほど かかり、正直「高い検査だな」と感じました。
幸い、そのときはがんの活動を疑わせる所見は見つかりませんでしたが、「もし全身転移を疑うときには、これほど有益な検査はない」と実感しました。PET-CTは決して頻繁に受けられる検査ではありませんが、必要なタイミングで受けることで安心や次の治療方針につながると思います。

まとめ
ここまで【病院でよく聞くけど実は意味を知らない医療用語10選・パート2】として、10の用語を解説してきました。
- 骨髄抑制
- ナディア
- 浮腫(むくみ)
- ケモブレイン
- 末梢神経障害
- 倦怠感(がん関連疲労)
- 味覚障害
- 感染予防
- 腫瘍マーカー
- PET-CT
どれも、がん患者さんやご家族が治療の中で必ずといっていいほど耳にする言葉です。けれど、ただ「聞いたことがある」だけでは不安が募ります。意味が分かり、どんなときに注意が必要かを知ることで、心構えができて少し安心できるのではないでしょうか。
私自身、患者として「腫瘍マーカーの数値」に揺れたり、「倦怠感は普通の疲れと違う」と実感したり、「感染予防の徹底が命を守る」と体感してきました。看護師として、患者さんに「骨髄抑制が出たときは無理しないで」と伝えてきたことが、今は自分自身への声掛けにもなっています。
がん治療は、体だけでなく心や生活にも影響を与える長い道のりです。だからこそ、言葉を知り、意味を理解することは、闘病を支える大きな力になります。
あなたが最近、医師や看護師から言われて「これってどういう意味?」と感じた言葉は何でしょうか?
ぜひコメントやメッセージで教えてください。きっと同じ疑問を抱えている人の助けになるはずです。
病院で飛び交う言葉を「わからないまま」ではなく「味方」にできるように。これからも一緒に学んでいきましょう。
🍀関連記事とおすすめ記事です
・ネオアジュバントをもしかしたらあなたも経験しているかも…あれがネオアジュバントだったのか!
・心も体も消耗しているがん患者だからこそ、看護師の一言が心に沁みることがあります。
・相手は励ますつもりだったけど・・・がん当事者はひどく傷ついてしまうことも!
・落ち込んでいるときに温かい言葉をかけられると、頬につらーっと涙があふれる時があります。
 看護師の私とがん闘病の物語
看護師の私とがん闘病の物語