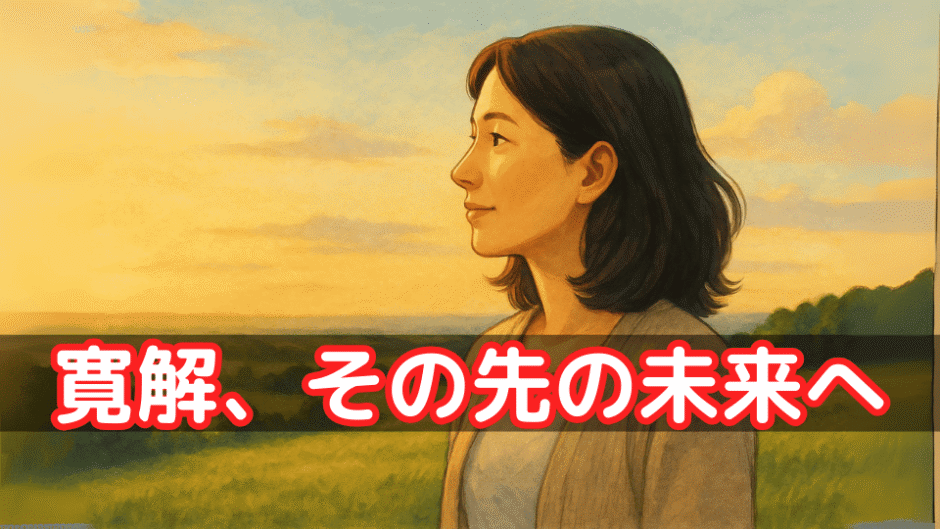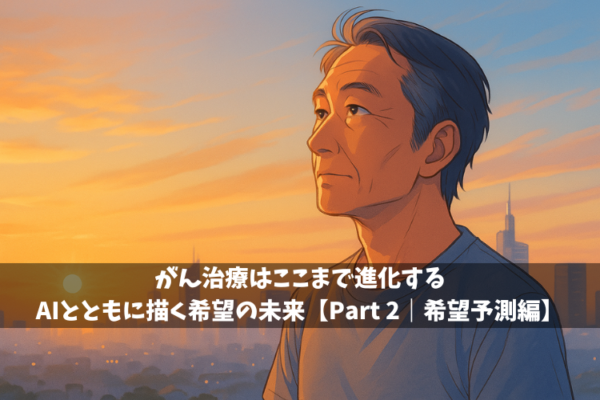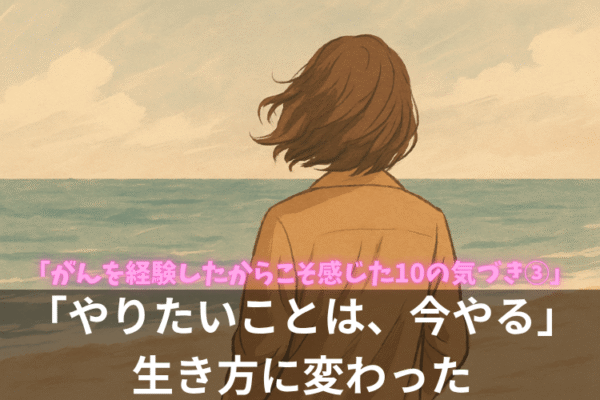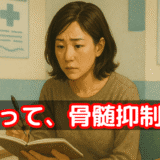がんの治療を受けていると、医師から「寛解」という言葉を耳にすることがあります。
けれど、「寛解って治ったことなの?」「完治とは違うの?」と疑問に思う方は少なくありません。
私自身も、がんと向き合っている今、「寛解」という言葉は一種の目標であり、憧れのような存在です。
「もし自分が寛解になれたら…」と想像すると、安心と不安が入り混じった複雑な気持ちが湧いてきます。
この記事では、がん患者やその家族に向けて「寛解」という言葉の意味を整理し、さらに保険や生活設計とどう関わるのか、そして患者としての本音も交えてお伝えしたいと思います。

「寛解」が使われる病気とは?
「寛解」という表現は、がんだけでなく、再発や再燃のリスクがある病気で用いられます。
- がん(悪性腫瘍)
血液がん(白血病・悪性リンパ腫など)では、治療効果を示す基準として「完全寛解」「部分寛解」という言葉が日常的に使われます。
固形がん(乳がん・胃がん・大腸がんなど)でも、腫瘍が画像上見えなくなったときに「完全寛解」と呼ばれることがあります。 - 膠原病や自己免疫疾患
関節リウマチや全身性エリテマトーデス(SLE)では、薬で炎症を抑え、症状がほとんど出ていない状態を「寛解」と表現します。 - 精神疾患
うつ病などでも「症状が落ち着き、社会生活に支障がない状態」を寛解と呼びます。
つまり、「今は症状がコントロールされているけれど、再発の可能性が残っている病気」に対して使われるのが「寛解」なのです。
なぜがんで「全治◯か月」と言わないのか
風邪や骨折などは「全治◯日」と表現されます。治療が終われば、再発のリスクがほとんどないからです。
一方でがんは、たとえ画像検査で腫瘍が見えなくなっても、体内に顕微鏡レベルの小さながん細胞が潜んでいる可能性があります。数年後に再発や転移として現れることもあります。
だからこそ、医師は「完治しました」とは言いません。
希望を持たせすぎると、再発時に患者と家族のショックが大きいからです。
その代わりに「寛解」という言葉を使います。
これは「今は病気が抑えられている」という前向きさと「今後の注意も必要」という現実の両方を含む表現。バランスの取れた言葉だといえます。

まあ、早く言えばがんは治らないってことだよね・・・
寛解と保険加入の関係(5年ルール)
ここからは実用的なお話です。
がん経験者にとって「寛解」して5年以上の長期寛かい状態が続けば、保険商品の加入への可能性が高まります。
多くのがん保険や医療保険には、
👉 「過去5年以内にがんでの入院・手術・治療歴がないこと」
という条件があります。
つまり、治療が終わり「寛解」となっても、5年間は新しい保険に入れないことが多いのです。
この「5年ルール」は医学的にも意味があります。
がんの多くは、治療後5年間に再発リスクが高いとされているため、その期間を経過したら「再発の可能性が低下した」と見なされるのです。
経済的に見ても「5年」は大きな区切り。
再発リスクが下がった寛解5年以降であれば、保険会社も「加入OK」と判断しやすくなるのです。

私の体験:献血と「5年ルール」
私は20歳の頃から献血を続けてきました。30年近くの間に93回。献血は、私にとって「誰かの役に立てる」という小さな誇りでした。
でも、がんになって調べてみると—— がん治療が終わっても、治癒後5年が経過するまで献血はできない と知りました。さらに、造血器腫瘍(白血病など)の場合は、たとえ5年経っても献血はできないそうです。
このとき、私は「保険と同じだ」と思いました。
献血も保険も、社会の中では「5年間再発や治療歴がないこと」が一つの基準になっているのです。
つまり「5年無事に過ごすこと=社会的に寛解と認められること」なのだと。
5年という長さと、再発率の現実
しかし、この「5年」という時間は、患者にとってとても長いものです。代表的ながんの再発率を見ても、5年以内に再発する可能性は決して低くありません。
- 大腸がん:全ステージ平均で約18.7%
ステージⅠでは約5〜6%、ステージⅡで約13〜15%、ステージⅢでは約30〜32% - 乳がん:全体で約20〜30%
ステージⅠで10%未満、ステージⅢでは30〜50% - 肝臓がん:50〜70%と非常に高い
- 膵臓がん:80%以上と極めて高い
- 食道がん:30〜50%
(出展:国立がん研究センター)
こうした数字を目にすると、「5年を待つ」ということがどれだけ難しいかを実感します。
患者としての本音——4年半の不安
正直に言えば、もし私が治療後4年半を無症状で過ごせたとしたら、こう考えてしまうと思います。
「あと半年で保険に入れる、住宅ローンも組める。だったら今は静かに過ごして、5年を迎えてからまとめて検査を受けよう」——と。
冷静に考えれば、検査を控えるのは再発の早期発見を逃す危険な行為だとわかっています。
でも「社会的に寛解と認められる5年」という壁があるからこそ、そこに意識が集中してしまうのです。
きっと同じように感じる患者さんは少なくないはずです。
「制度」と「命を守る医療」のはざまで揺れる——これが、がん患者としての私の本音なのです。

寛解がもたらす生活設計のチャンス(住宅ローン・家計・働き方)
「寛解」は医学的な意味だけでなく、人生設計を立て直すチャンスでもあります。
- 住宅ローンの審査
がん治療中や直後はローン審査に通らないケースがほとんどです。
しかし、寛解から一定期間(5年)が経てば、審査を受けられる可能性が広がります。団信(団体信用生命保険)付きの住宅ローンも、再挑戦できるチャンスが生まれます。 - 保険の見直し
寛解5年を経過すれば、がん保険や医療保険に再加入できるケースがあります。
「一度がんになった自分はもう保険に入れない」とあきらめるのではなく、条件を満たした時点で情報収集をしておくと安心です。
👉 保険を比較するサービスを利用して確認してみる
30社以上の【がん保険】から希望に合ったプランを専門家が探してくれるベビープラネットのがん保険相談サービス - 働き方の再設計
寛解は「再出発」の合図でもあります。
「フルタイムで働くのか」「在宅ワークや副業を取り入れるのか」など、体力や生活に合わせた新しい働き方を考えるタイミングでもあります。
私にとっての「寛解」という未来像
私はいま「寛解」という言葉を医師から告げられたことはありません。
だからこそ、寛解は「憧れ」であり「目標」なのです。
もしその日が来たら、私はきっと安心すると同時に、また不安にもなるでしょう。
「本当に大丈夫なのかな?」「また再発するのでは…」
そんな気持ちが入り混じるのが「寛解」という言葉の現実です。
けれど同時に、寛解は 生活設計を見直すチャンス をくれる言葉でもあります。
保険に入り直せるかもしれない、住宅ローンを組めるかもしれない、仕事や暮らしを立て直せるかもしれない。
寛解という言葉は、医学的な意味を超えて、人生の未来を描き直すための節目の言葉だと感じています。

まとめ
- 寛解は「再発の可能性を残したまま症状が落ち着いた状態」
- がんでは「完治」ではなく「寛解」という言葉を使う
- 保険や住宅ローンには「5年ルール」があり、寛解が大きな意味を持つ
- 5年という時間は患者にとって重荷であり目標でもある
- 寛解は安心と不安が混ざり合う言葉であり、人生を再設計するチャンスでもある
👉 あなたにとって「寛解」とはどんな意味を持ちますか?
「もし寛解になったら、どんなことをしたいだろう?」
そんな問いかけが、未来を描く第一歩になるかもしれません。
🍀関連記事をご紹介します
 看護師の私とがん闘病の物語
看護師の私とがん闘病の物語